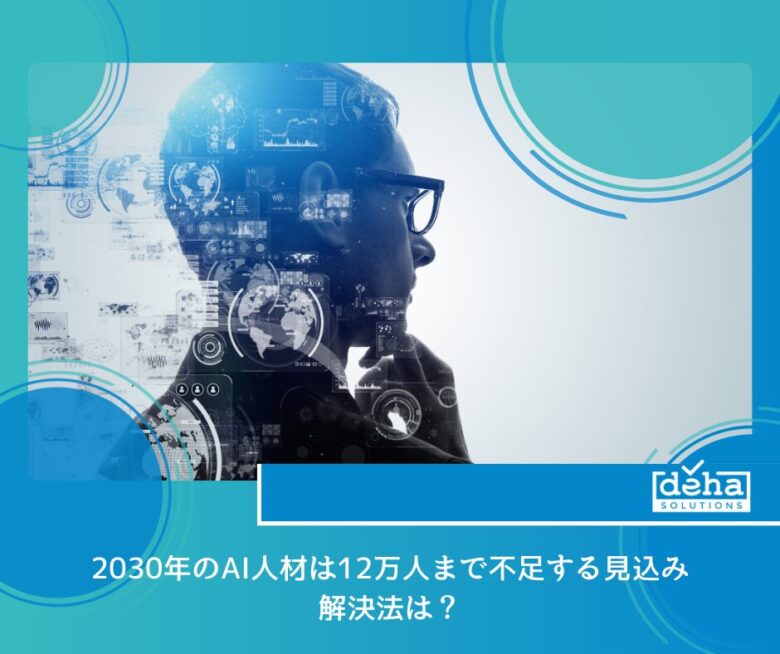deha magazine / AI / 生成AIサービスの導入形態:3つのタイプと最適な選び方
生成AIサービスの導入形態:3つのタイプと最適な選び方
2025/08/16

近年、生成AI(Generative AI)は文章生成、画像生成、音声合成、プログラムコードの自動生成など、幅広い分野で実用化が進んでいます。
業務効率化や新しい価値創造の手段として注目され、さまざまな業種で導入が加速しています。
しかし、生成AIサービスを導入するにあたり、どのような形態で利用するかは企業の戦略や要件によって異なります。
この記事では、主な導入形態としてSaaS型の生成AIサービス、オンプレミス型生成AIサービス、API/PaaS活用型生成AIサービスに着目し、それぞれの特徴・メリット・デメリット・選び方のポイントを整理します。
- 生成AIサービスを導入したい方
- 生成AIサービスのタイプを知りたい方
- 社内のIT人材が不足している方
これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めば生成AIサービスについてどんな特徴があるのかがわかるのはもちろん、適切な選び方まで丸わかりですよ。
1. SaaS型の生成AIサービス
特徴
SaaS(Software as a Service)型は、クラウド上で提供される生成AIサービスを、インターネット経由で利用する形態です。
ユーザーはWebブラウザや専用アプリを通じてアクセスし、契約プランに応じて利用できます。
ChatGPTやClaude、Midjourney、Jasperなど、すでに多くの生成AIがSaaSとして提供されています。
メリット①導入の容易さ
インフラ構築や環境設定が不要で、アカウント登録後すぐに利用開始できます。初期の設定作業が不要なため、業務現場へのスムーズな展開が可能です。
メリット②初期費用が低い
サブスクリプション型が多く、初期投資を抑えることができます。必要な機能や利用規模に応じて柔軟に契約でき、コスト効率の高い運用が実現します。
メリット③自動アップデート
最新モデルや機能を自動で利用可能。常に最新の性能とセキュリティ環境でサービスを活用でき、メンテナンスの負担も軽減されます。
メリット④スケーラビリティ
利用ユーザーや処理量の増減に柔軟に対応。成長段階や繁忙期などの需要変動にもスムーズに適応でき、安定した業務運用を支えます。
デメリット①カスタマイズ性の制限
SaaS型サービスは提供側が用意した機能・設定範囲内での利用となるため、業務プロセスや独自要件に完全に合わせた細かなカスタマイズは難しい場合があります。
特に専門的な業務や独自のワークフローを持つ企業では、機能不足や仕様の不一致が生じる可能性があります。
デメリット②データ管理の制約
機密情報や個人情報の取り扱いは、サービス提供側のセキュリティポリシーや法的規制に準拠する必要があります。
データ保存先が海外の場合、国や地域ごとの法制度の違いによるコンプライアンス対応が課題となることもあります。
デメリット③依存リスク
ベンダーの仕様変更、機能削除、価格改定などの影響を直接受けやすく、自社の運用計画やコスト見積もりに影響を及ぼすことがあります。
極端な場合にはサービス停止や終了による業務への影響も懸念されます。
向いているケース
- 迅速に生成AIを業務へ取り入れたい場合
- 専門的な開発リソースを持たない中小企業
- 試験的・パイロット的に生成AIを導入したい場合
2. オンプレミス型生成AIサービス
特徴
オンプレミス型は、自社のサーバーやデータセンターに生成AIのモデルやシステムを構築・運用する形態です。
インターネットに接続しないクローズド環境でも運用でき、セキュリティやコンプライアンス要件が厳しい組織で選ばれます。
メリット①高度なセキュリティ
データが外部クラウドを経由せず、すべて社内環境で処理されるため、機密情報や個人情報の漏えいリスクを最小限に抑えられます。
金融機関や医療機関など、高度なセキュリティ基準を求められる分野でも安心して運用できます。
メリット②完全な制御権限
AIモデルの構造や学習データ、推論環境などをすべて自社のポリシーやニーズに合わせて自由に設定できます。
外部サービスの仕様変更や停止の影響を受けず、長期的かつ安定的な運用が可能です。
メリット③カスタマイズ性
業務特化型のモデル設計や専門用語への最適化、独自データによる追加学習など、精度や利便性を大幅に向上させる調整が可能です。
これにより、汎用AIでは難しい高精度な業務支援や意思決定支援を実現できます。
デメリット①高コスト
高性能GPUを備えたサーバー設備の購入やデータセンター環境の整備、さらに専門知識を持つ保守・運用担当者の確保など、多額の初期投資が必要です。
加えて、電力消費や部品交換、保守契約といった継続的な運用コストも大きく、長期的な予算計画が欠かせません。
デメリット②導入期間が長い
システム設計、ハードウェア調達、環境構築、モデルの学習・検証といった各工程に時間を要するため、クラウド型と比べて稼働までのリードタイムが長くなります。
特に大規模モデルでは学習期間も含め、数か月以上かかる場合があります。
デメリット③アップデート負担
生成AIの進化は非常に速く、新しいモデルや機能が次々登場しますが、オンプレミスではこれらを自社で検証・導入しなければなりません。
外部サービスのように自動更新されないため、最新性能を維持するには継続的な技術フォローと人員リソースが不可欠です。
向いているケース
- 金融、医療、防衛など、高度な情報保護が必須の分野
- 法規制や業界基準によりデータ外部持ち出しが禁止されている企業
- 大規模なAI開発・運用基盤を自社で保有している組織
3. API/PaaS活用型生成AIサービス(柔軟な開発とカスタマイズ)
特徴
API(Application Programming Interface)やPaaS(Platform as a Service)を利用し、生成AI機能を自社システムやアプリケーションに組み込む形態です。
OpenAI APIやGoogle Cloud Vertex AI、Azure OpenAI Serviceなどが代表例です。
メリット①柔軟な統合
既存システムやワークフローにシームレスに組み込み可能です。
APIを介して社内ツールや外部サービスと容易に連携でき、業務プロセスを大きく変えずに生成AIを活用できます。
段階的な導入や部分的な機能追加も可能なため、現場の負担を最小限に抑えつつ効率化を実現できます。
メリット②高度なカスタマイズ
プロンプト設計やファインチューニングで業務特化モデルを構築できます。
専門用語や社内ルールを反映させることで、精度と実用性を高められるほか、業界特有の規制やセキュリティ要件にも対応可能。
用途ごとに異なるモデルや応答形式を設定でき、ビジネスニーズに即した最適化が行えます。
メリット③スケーラブルな開発
クラウド基盤を活用し、大規模処理にも対応です。
アクセス負荷の増加やデータ量の拡大にも柔軟にスケールアップでき、グローバル展開や急速な利用拡大にも耐えられます。
リソースの自動拡張や監視機能により、安定した稼働とコスト最適化を同時に実現できます。
デメリット①開発リソースが必要
エンジニアリングやAPI連携の知識が求められます。
要件定義から設計・実装・テストまでの開発工程に専門人材が関与する必要があり、スキル不足の場合は外部委託や人材育成が不可欠となります。
また、運用開始後も仕様変更や機能追加への対応が求められるため、継続的な開発体制が必要となります。
デメリット②利用料金の変動
API呼び出し回数や処理量に応じた従量課金でコスト予測が難しい場合があります。
特にアクセス急増や想定外の利用拡大が発生した場合、月額費用が急上昇するリスクがあるため、利用制限やモニタリングを組み合わせたコスト管理が不可欠です。
デメリット③外部依存
クラウドベンダーのサービス停止や価格改定リスクを受けます。
API仕様の変更や提供停止によって、自社サービスの機能停止や改修負担が発生する可能性があり、冗長構成や代替サービスの検討などリスク分散策が必要となります。
向いているケース
- 自社サービスや製品に生成AIを組み込みたい企業
- 既存業務システムと連携して業務効率化を図りたい場合
- 柔軟なモデル選択や拡張性を重視するプロジェクト
最適な選び方のポイント
1. セキュリティ要件の確認
業界規制や社内ポリシーに基づき、データが外部に出せるかを明確にします。
機密情報を扱うならオンプレミス型や高セキュリティのAPI活用が適しています。
2. 利用目的と規模感の把握
小規模な試験導入ならSaaS型、大規模かつ事業基盤に組み込むならAPI/PaaS型、厳密なデータ管理が必要ならオンプレミス型が有力候補です。
3. コスト構造の分析
初期費用だけでなく、運用費用・従量課金・モデル更新コストまで含めて比較検討します。
4. 社内リソースとスキルセット
エンジニアリング体制やデータサイエンティストの有無によって、開発型(API/PaaS)か既製型(SaaS)の適合度が変わります。
5. 将来の拡張性
現在の利用規模だけでなく、数年先の利用拡大や新サービス展開にも対応できる形態を選びましょう。
まとめ
いかがでしたか。本日は生成AIサービスの導入形態について3つのタイプと最適な選び方を紹介していきました。
生成AIの導入形態は、大きく分けてSaaS型、オンプレミス型、API/PaaS活用型の3つがあります。
それぞれに長所と短所があり、どれが最適かは企業の目的・規模・セキュリティ要件・開発体制によって異なります。
まずは小規模なSaaS型で試験導入し、効果を確認した上でAPI連携やオンプレミスへの移行を検討する「段階的導入」も有効です。
生成AIは進化のスピードが速いため、柔軟性を持った選択と継続的な見直しが成功の鍵となります。