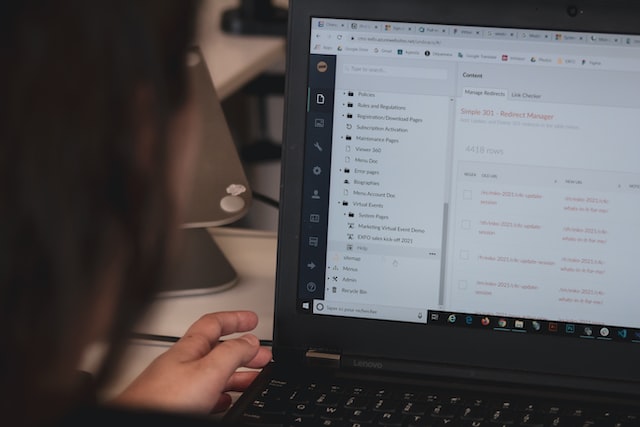deha magazine / オフショア開発
オフショア開発
開発効率アップ!APIを活用したシステム開発とは?
AP Iとは、2つのアプリケーションやソフトウェア同士の情報のやり取りの際に、プログラミング上で窓口になる場所のこと。 APIを活用することで既存の機能を自社システムに取り入れることができ、その分を1から開発する必要がなく、データ収集も不要。 開発効率を大きく上げることができるのです。 この記事ではそんなAPIに関してどんな仕組みなのか、どんなサービスがあるのかなど徹底解説していきたいと思います。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばAPIがどんな仕組みなのかはもちろん、そのメリットやデメリットまで丸わかりですよ。 AP Iとは AP Iとは「Application Programming Interface」のことで、2つのアプリケーションやソフトウェア同士の情報のやり取りの際に、プログラミング上で窓口になる場所のことを指します。 ソフトウェアの一部をWEB上に公開し、それを外部の人が利用することで、自分のソフトウェアに他のソフトウェアの機能を埋め込むことが可能になります。 API自体はWEB上に公開されているので、誰でも無料で利用することができます。 外部のソフトウェアの機能を利用するといっても、内部のコードまでは公開していません。つまり外部からは機能の使い方がわからないため、使い方やルールもあわせて公開されているのが一般的です。 APIの仕組み APIサービスを利用する人は事前に定められた形式に従って、使いたい機能や情報をリクエスト(要求)します。するとサービス側はリクエストを受け取り、送信された条件を処理してレスポンス(応答)を行います。 リクエストの内容はAPIサービスの提供者が情報をまとめて定義し、利用者に提示します。 APIの種類 WEB API APIのうち、多くがインターネットを経由してやりとりが行われます。これをWEB APIと呼びます。広く利用されているため、ネット上の記事ではAPI=WEB APIとして取り扱っているものも多く存在します。 WEB APIはインターネット上で情報のやり取りに使われるHTTP/HTTPSを使用して、アプリケーション同士の連携を行います。 使用されるプログラミング言語の仕様にとらわれずに利用できるのが魅力です。 OSのAPI APIの中にはOS上でプログラミングを行うために用意されているAPIも存在します。 例えばWindowsAPI。WindowsAPIはその名の通り、Windows上でプログラミングをするために用意されたAPIです。 具体的には、様々なアプリケーションソフトが共通して使える機能を提供します。例えばウィンドウやフォントなど共通した機能を提供することで各種アプリケーションソフトの製作者は、全ての機能を作り込む作業から解放されます。 ランタイムのAPI プログラムを動かす環境であるランタイムが提供するAPIも存在します。例えばプログラミング言語のJavaはアプリケーションの開発に必要な標準機能がAPIとして提供されています。 このAPIがあればJavaでより効率的に作業をすることが可能です。Java SE APIの仕様については、Javaの開発を行なっているアメリカのオラクル社が提供する開発者ガイドの中で詳しく紹介されています。 Java学習者はAPIのドキュメントの構造や読み方を確認しておくと良いでしょう。 APIの活用事例 Facebook API Facebook APIはFacebookが提供しているAPIです。インスタグラムなどで利用されています。Facebook APIを利用することで、Facebookの友達がインスタグラムに登録した際に、通知がきたり、投稿のお知らせを送ることができます。 LINE API LINE APIはチャットボットの開発や、LINEでのログイン機能、IoT開発、音声アシスタント、LINE決済機能、ソーシャルボタン・通知機能などと言った機能を利用することができます。 このようにLINEは、Web開発に使えるものだけでなく、IoT開発など幅広い機能を公開しています。 特にチャットボット機能はLINEのトーク画面を利用して、ユーザーの反応に応じてあらかじめプログラムしておいた処理が可能というもの。 多くのサイトで利用されていて、使い方によってはお客様サポートの効率化に繋がります。 YouTube API YouTube APIでは動画の効果測定や制御、チャンネルデータの一括取得などと言った利用が可能です。 特にチャンネルデータの一括取得では、動画のタイトル、再生回数、いいね数などはもちろん、チャンネルの登録者数、チャンネルの再生リストなどの情報を取得することができます。 […]
続きを読む >>
ベトナム人IT人材が品質管理の面で他のオフショア先よりも優れている理由
ベトナム人IT人材の品質管理は他のオフショア国と比べ高いと言われています。 そもそもオフショア開発は中国やインドで広がり、今や東南アジアの多くの国で行われています。 なぜそれらのオフショア国と比べ、ベトナムは高いレベルの品質管理が行われているのでしょうか。 この記事ではそんなベトナムオフショアの品質管理に関して徹底解説していきます。 ベトナムオフショアが気になる方 品質の高い開発を外注したいと考えている方 社内のIT人材が不足している方 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばベトナムオフショアの品質管理の秘密が丸わかりですよ。 品質管理の重要性 オフショア開発において、プロジェクトの品質向上を目指すには品質管理チームが重要な役割を果たします。 品質管理チームとは、お客様が安心して気持ちよく商品を利用できるよう調査・管理するチームのことを指します。 要件定義の段階から参加することで開発期間と同時に要件を元にしたテストコードやテストケースを作成することが可能になります。これにより、開発チームからの依頼を受けても手早くテストを行えるのです。 一方、オフショア開発を依頼した企業がオフショア開発先に感じた課題は何かというアンケートによると、「品質管理」や「コミュニケーション力」が課題になっていることがわかります。 品質管理は重要ではあるものの、課題としている企業が多くあることがわかりますね。 ベトナムの品質管理 そんな品質管理ですが、ベトナムでは高い品質管理を行なっています。オフショア開発白書がオフショア開発企業100社に行なったアンケートによると、ベトナムのオフショア開発企業は「日本人対応」や「技術力」といった他の項目以上に「品質管理・プロジェクト管理」を強みに挙げるケースが最も多かったことが分かりました。 高い品質管理の秘密 オフショア開発を成功に導くためには、技術力やコスト管理のほかにも、顧客と開発会社間のコミュニケーションギャップの解決などといったオフショア開発に絡むさまざまな課題を熟知し、柔軟に対応する品質管理が重要だということがわかりましたね。 ところで、ベトナムの品質管理の高さはどこからきているのでしょうか。ここからはベトナムオフショアが高い品質管理である理由を紐解いていきます。 ベトナム人の性格 ベトナム人には以下のような性格があると言われています。これは高い品質管理を保つ上で重要な性格と言えます。それぞれ詳しく見ていきましょう。 器用 向学心旺盛 交渉上手 交渉力の高さ 器用 ベトナム人は手先が器用なため、サプライチェーン移転場所として注目を浴びています。これまで多くのグローバル企業は中国で生産活動を行なってきましたが、サプライチェーンの一部をベトナムへと移転しているのです。 また最近ではハイテク機器などの高付加価値の製造移転も進んでいます。サムスンは2008年にベトナム北部に6億7,000万ドルの携帯電話製造工場を設立。その後10年間でベトナム全国に173億ドルを投資しました。その影響か、ベトナムは世界第2位のスマートフォン輸出国となったそうです。 向学心旺盛 ベトナムは転職が当たり前の社会で、社会人になってからもスキルアップを目指す若者が多くいます。 こちらのグラフは各国の社外学習・自己啓発を行なっていない人の割合を表しています。日本は残念ながら約半数の人が社外学習を行なっていないですが、ベトナム人はわずか2%のみ。多くの人が社外学習・自己啓発を行なっていることがわかります。 こうした向上心が高い品質管理につながっているのですね。 交渉力の高さ 品質管理をしっかりと行うためには、顧客の希望をしっかりと聞き取るヒアリング力や交渉力が重要です。 ベトナムでは価格交渉を前提とした生産市場があり、話し合いの文化が古くから根付いています。また、歴史的にも中国やフランス、米国とも戦火を交えた国であることから外交でもバランス感覚を重視した交渉が行われています。 こうした背景から交渉力が高く、話し合いの文化が築かれています。 女性が活躍 ベトナムでは共働きが基本で、女性が社会の中で活躍しています。世界経済フォーラム(WEF)が発表している「グローバル・ジェンダー・ギャップ指数」(The Global Gender Gap Index=GGGI)によると、ベトナムは146か国83位で、日本の116位と比べると高い数値となっています。(参照:Global Gender Gap Report 2022) 人材不足が深刻化する日本と比べるとわかりやすいですが、女性の就労促進は経済成長にもつながります。 また、最近の研究では、女性が活躍する企業の方が総資産利益率(ROA)や全要素生産性(TFP)といったパフォーマンスが高いことが明らかになっているのです。 国策としてのIT教育 ベトナムでは政府がICT教育を推進していて、2030年にはITエンジニアを含めた150万人のIT人材輩出を目指しています。 STEM教育という科学、技術、工学、数学に力を入れた教育を進めていて、中学校からコーディングやIT科目を学ぶようです。 IT関連の教育を展開している大学が30校近くあり、エンジニアになる人は毎年5万人ほどいると言われています。 ベトナム人エンジニアの平均年齢は31歳と若いのが特徴です。日々発展する新しいテクノロジーをキャッチアップする能力が高く、高度IT人材の割合も高いと言われています。 日本語能力の高さ 国際交流基金がまとめた「2018年度 海外日本語教育機関調査報告書」によると、ベトナムにおける日本語学習人口は2018年時点で約17万5,000人と世界6位にランクしています。 […]
続きを読む >>
オフショア開発とは?ベトナム企業に発注するメリット・各国の価格相場の比較も解説
オフショア開発とは人件費の安いグローバル人材を活用して、ソフトウェア開発をアウトソーシングする開発手法です。 日本のIT人材不足が問題視される中、IT人材の確保だけでなく、開発効率アップやグローバルな観点が取り入れられるということで注目されています。 特に注目するべき国はベトナムです。ベトナムは国策としてIT人材の教育を行っていて、毎年IT関連学科から約5万人のエンジニアが輩出されています。 この記事ではそんなオフショア開発に関して主要なオフショア開発国の比較や、ベトナムオフショア企業に発注するメリットなど徹底解説していきます。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばオフショア開発がなぜ注目されているのかを知れるのはもちろん、具体的なコストも丸わかりですよ。
続きを読む >>
ラボ型開発(ラボ契約)とは?メリット・デメリット、請負型開発との違いをご紹介
前回は、ラボ型開発の基礎的な知識についてお話しました。 今回は、そのメリット・デメリットについて簡単に説明したいと思いますので、下記の記事をどうぞご覧ください!
続きを読む >>
【見積り・相場を徹底解説!】Shopify(ショッピファイ)とは?【カスタマイズ力抜群!】
shopifyは社内にIT人材がおらず、EC構築が難しいスタートアップの会社などでおすすめのネットショップ作成ツールです。 この記事では、 「ECサイトを作りたいけどコストを下げたい」 「shopifyって本当に低コストで運用できるの」 などの疑問に思っている方向けに、Shopifyの特徴から費用、相場までを徹底解説していきます。 お見積りの際の参考にしてください。 shopify(ショッピファイ)とは Shopifyとは自社ECサイトの開発および運営を実現するプラットフォームとして、世界中で広く利用されているサービスです。世界で170を超える国が利用しており、これまで100万以上のECショップ導入実績があります。 従来のECサイト展開方法では、「自社サーバの用意」「パッケージの導入」などの事前準備に多くリソースを割く必要がありました。 その点、Shopifyはサブスクリプションをベースにしているため、従来までのような初期コストをかけずに、迅速に開発できることが大きな特徴となっています。 実際にShopifyでECサイトを構築する際には、「Shopify管理画面」で操作するだけで簡単に作成することができます。 それに加えて、様々なECプラットフォームと比較してShopifyが特に優れている点は「デザイン性」と「カスタマイズ性」にあります。 あらかじめ用意された「テーマ」を選択するだけで用途に応じた最適なデザインを簡単に実現でき、テーマに少し手を加えることで細かな要望に応じることも可能です。 無料見積もりはこちらから▶ プラン別!shopifyにかかる費用 ECサイトプラットフォームを選ぶ上で重要な月額費用。ここからはshopifyの費用についてまとめました。 shopifyは以下の4つのプランに分かれています。 ベーシックプラン スタンダードプラン プレミアムプラン shopify+(プラス) それぞれのプランごとに費用や機能が異なるため、自分に合っているプランを見つけてみましょう。 プラン 月額利用料 特徴 このプランが向いている方 ベーシックプラン $25(約3,360円) ・基礎的なECサイトの構築が可能・多彩なテーマから用途に応じたECサイトを簡単にデザイン可能・スタッフアカウント数が2つまで(※小規模ストア向き)・財政レポート、集客レポート、マーケティングレポートが利用可能 ・事業そのものが初期段階の方・ECサイトに初挑戦する方試験的な使用を目的とした方・とにかく運用費を重視している方 スタンダードプラン $69(約9,270円) ・ベーシックプランで可能だった機能はスタンダードプランでも可能・スタッフアカウント数が5つまで(※中規模ストア向き)・ベーシックプランよりもレポートの種類が拡充される(※リピーター分析、国家単位分析などのさらに進んだ顧客分析が可能) ・リアルな販売店舗を運営しつつ、ECサイトも同時展開する方・複数の従業員で運用および管理をする方 プレミアムプラン $299(約40,190円) ・月額利用料は最も高額だが、取引手数料が最も安価(※売上規模が大きくなるほど、相対的にプレミアムプランがお得になる)・スタッフアカウント数が15つまで(※大規模ストア向き)・スタンダードプランよりも、さらに高度な分析が可能(※Web上での顧客流入経路が分析可能。Google広告から来たの顧客が多いのか、それともinstagramから来た顧客が多いのかなどが把握できる) ・他のECサイトの開発・運用経験のある方・SEO対策や流入経路分析など、Webマーケティングに注力したい方・事業収益が大きい方 shopifyには、更に規模の大きな会社用のshopify+、月額約1200円で始められるshopify Lightの2つのプランが追加で用意されています。 shopifyの費用の大きな特徴は、初期費用がかからず、いつでもプランを変更することができる点です。 無料見積もりはこちらから▶ shopifyでのサイト構築費用の相場 個人・企業に関わらず簡単にECサイトを作成し運営することができるのがShopifyの強み。 しかし、本格的にECサイトを作成・リプレイスを検討される場合に気になるのが「制作会社に依頼する場合の相場」 ここからは「制作会社に依頼する場合の相場」についてまとめています。 相場1:約50万円~100万円 shopifyの導入のカスタマイズなどを行ってくれます。初期設定などは個人でも行う事ができますが、より適切なアプリ設計やデザインなどを行うことができます。例としては以下のような作業を行ってくれます。 例 アカウント取得 ドメイン設定 公式テーマを用いたサイトのデザイン カスタマイズ(提供された素材の編集) 商品登録 決済設定 […]
続きを読む >>
【注目】アジャイル開発とは?オフショア開発に効果的!?
現在、「アジャイル」はIT業界の開発だけではなく、様々なビジネス分野でも注目され始めています。なぜ世界中でアジャイル開発が主流になってきているのでしょうか? 今回はアジャイル開発の概要を解説してみたいと思います。
続きを読む >>
Shopify(ショッピファイ)の構築費用は高い?【失敗しない為の相場情報】
ECサイトの構築手段として、最近話題になっているのがShopifyです。 Shopifyは安全で高機能なECサイトをローコストで素早く立ち上げることができるプラットフォームです。 現在、世界中で大注目されており、一番成長しているECプラットフォームと言っても過言ではありません。 そんな、Shopifyですが、実際にプロの制作会社に構築を依頼する場合、どのくらい費用がかかるのでしょうか。 結論から言うと、Shopifyの構築を外注すると30万円〜1000万円程度かかります。 費用はどのようなECサイトを構築するか、どこに頼むかで変わってきます。 当記事では、shopify構築の相場や、ECサイトの構築する際の制作会社の選び方まで解説します。 「shopifyの構築の相場が知りたい」 「shopifyの構築はどんな制作会社に頼めばいいの?」 このような疑問をお持ちの方、必見です。
続きを読む >>
【実績まとめ】オフショア開発でcms構築
オフショア開発でCMS構築をすると、国内で開発を行うよりもコストを抑えることが可能です。 DEHAソリューションズでもCMS構築の実績がございます。 そこでこの記事ではオフショア開発のCMS構築に関して、DEHAソリューションズの実績をご紹介しながらその特徴について解説していきたいと思います。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばCMS構築をオフショア開発で行うメリットなど丸わかりですよ。
続きを読む >>
【実績まとめ】オフショア開発でハイブリッドアプリ
ハイブリットアプリは「Webアプリ」と「ネイティブアプリ」の良いところを組み合わせた近年注目のアプリです。 OSに依存することなく、1つの開発でiOSやAndroidどちらにも対応させていくことが可能。 この記事ではそんなハイブリットアプリに関して、DEHAソリューションズでオフショア開発をした実績も交えながら解説していきたいと思います。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばオフショア開発でどのようなサービスが開発できるのか、ハイブリットアプリの特徴は何なのかなど丸わかりですよ。