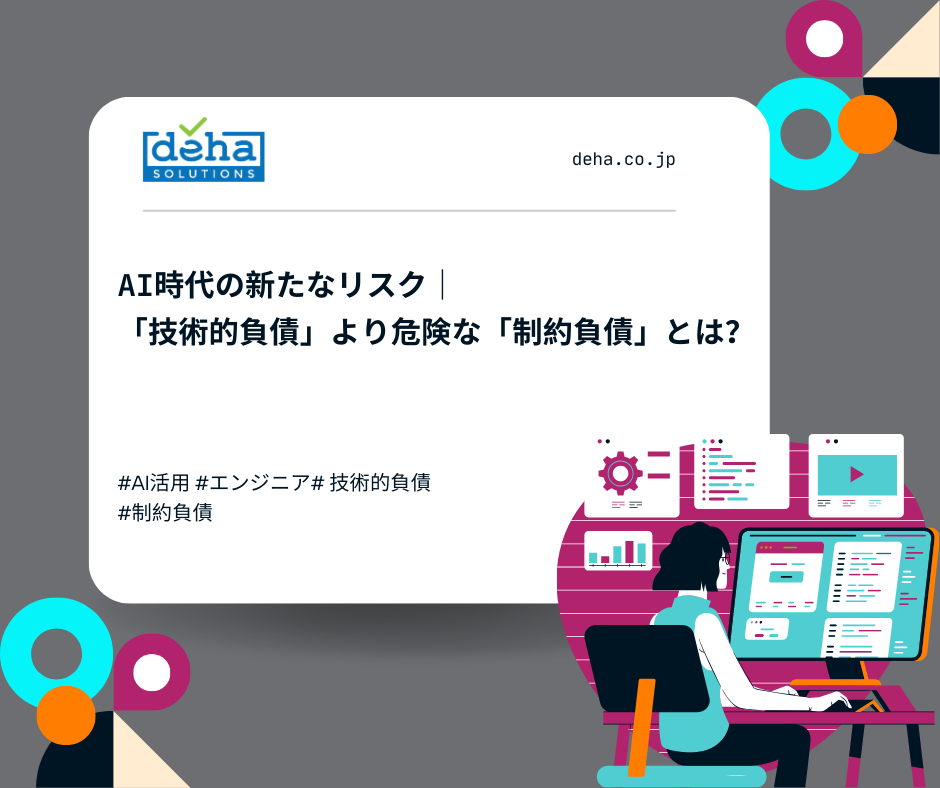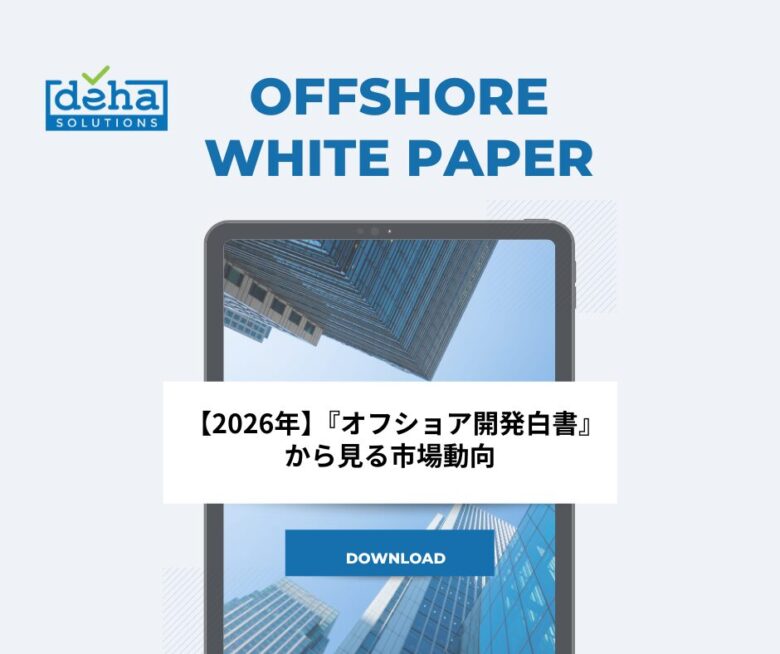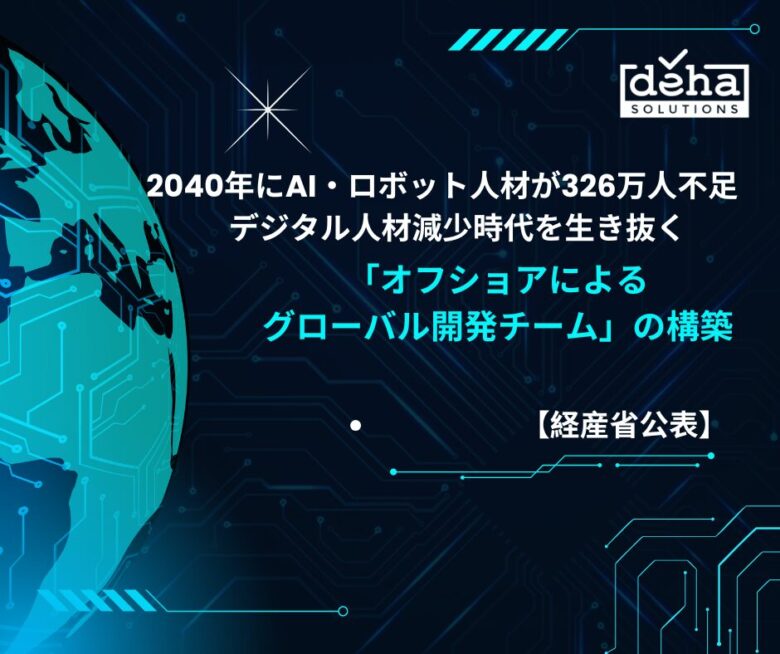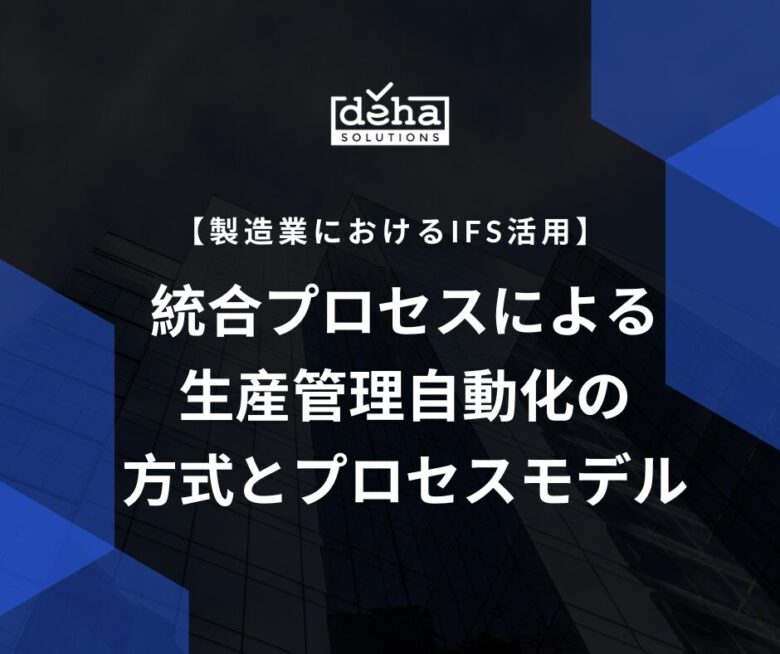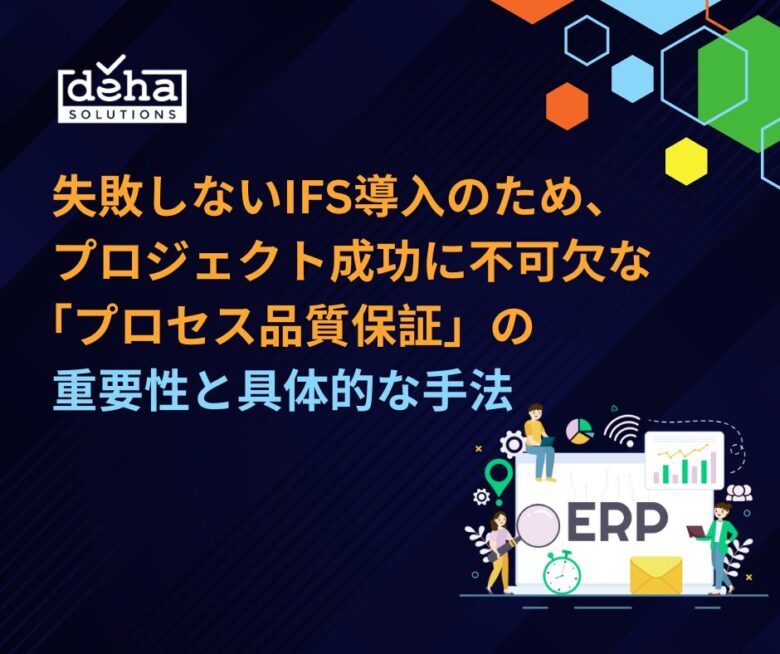AI時代の新たなリスク|「技術的負債」より危険な「制約負債」とは?
ソフトウェア開発の世界において、「技術的負債(Technical Debt)」という言葉は数十年前から馴染みのある概念です。スピードを優先した不適切なコードや設計が、将来的に修正コストやバグの増大を招くことは、エンジニアやマネージャーにとって共通認識となっています。 しかし、AI活用が急速に進む現代において、技術的負債よりもはるかに深刻で、目に見えにくい新たなリスクが蓄積されつつあります。それが制約の負債(Constraint Debt)」です。 本記事では、最新テクノロジーの実装において見落とされがちなこの概念と、その対策について解説します。
続きを読む >>
【2026年】『オフショア開発白書』から見る市場動向
国内IT人材不足、円安の長期化、開発スピードへの要求高度化。 こうした環境変化の中で、オフショア開発は一時的な選択肢ではなく、日本企業の開発戦略における「前提条件」となりつつあります。 本記事では、2025年に実施された各種調査データを基にした『オフショア開発白書』の内容を整理しながら、2026年に向けたオフショア開発市場の動向を読み解いていきます。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばオフショア開発の最新の動向が丸わかりですよ。キーワードは「拡大」「成熟」「戦略化」です。 関連記事: 【2025年】『オフショア開発白書』から見る市場動向 【2024年版】オフショア開発国のランキング|委託先国の特徴とは? 【2023年版】オフショア開発白書から読みとくオフショア開発の現状と最新の市場動向
続きを読む >>
【製造業におけるIFS活用】統合プロセスによる生産管理自動化の方式とプロセスモデル
近年、製造業はかつてないほどの環境変化に直面しています。 需要変動の激化、多品種少量生産への対応、グローバルサプライチェーンの複雑化、人手不足、原材料価格の高騰など、経営・現場の両面で不確実性が増大しているのです。 このような状況下において、多くの企業が課題として挙げるのが生産管理の属人化・分断化です。 これらの問題は、部分最適なシステム導入や、部門ごとに分断された業務プロセスによって引き起こされることが多いです。 こうした背景の中で注目されているのが、IFS(Industrial and Financial Systems)を活用した統合型生産管理の自動化。 この記事では、IFSの特長を踏まえながら、製造業における生産管理自動化の方式と、それを支えるプロセスモデルについて詳しく解説していきます。
続きを読む >>
IFSオフショアサービスの最適解|ベトナムから提供する高品質・高効率なアジャイルの開発体制確保
近年、製造業、エンジニアリング業、エネルギー、サービス業を中心に、ERPパッケージ「IFS」の導入・活用が急速に進んでいます。 IFSは、EAM(設備資産管理)、FSM(フィールドサービス管理)、製造、サプライチェーン、プロジェクト管理など、現場業務に強いERPとして評価されており、グローバル展開を前提とした柔軟なアーキテクチャを特徴としています。 一方で、IFS導入プロジェクトやその後の保守・改修フェーズにおいて、以下のような課題を抱える企業も少なくありません。
続きを読む >>
【保存版・発注者向け】アプリ開発の方法についてゼロから解説
アプリ開発を検討する企業や個人にとって、最初に直面する課題は「どのようにアプリを作るか」です。 そこで本記事ではアプリ開発について、どのような工程があるのかゼロから徹底解説していきたいと思います。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばアプリ開発の効率の良い方法が丸わかりですよ。 アプリ開発に関わるすべての工程や手法を理解することで、発注者としてより良い判断ができ、プロジェクトを円滑に進めることが可能になります。
続きを読む >>
【2025年版】スマホ(iPhone/Android)OS端末シェアランキング(世界と日本市場)
スマートフォン市場におけるOS(オペレーティングシステム)は、ユーザー体験の根幹を担う要素のひとつです。 特に「Android」と「iOS」の二大OSは、長年にわたって競争を続けており、地域によってその勢力図は大きく異なります。 この記事では、2025年4月時点における世界および日本のスマホOSシェアを、StatCounterの最新データをもとに詳しく解説します。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めば世界と日本のOSシェアの特徴や違いが丸わかりですよ。
続きを読む >>
【2026年版】ベトナム デジタル状況、最新動向
2026年のベトナムは、東南アジアの中でも特に「デジタル化が成熟段階に入りつつある国」として注目を集めています。 スマートフォンの普及、ソーシャルメディアの浸透、高速通信インフラの整備、そして若く人口ボーナス期にある社会構造が相まって、デジタル技術はすでに人々の日常生活、経済活動、情報収集の中核となっています。 この記事では、DataReportal「Digital 2026 Vietnam」レポートをもとに、2026年のベトナムにおけるデジタルデバイス、インターネット、ソーシャルメディア、主要プラットフォームの利用状況とその背景、そして今後の方向性について総合的に解説していきます。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばベトナムのデジタルの最新情報や動向が丸わかりですよ。 関連記事: 【2024年版】ベトナムのDX市場の状況と動向 2025年のベトナム デジタル状況、最新動向
続きを読む >>
ベトナムAI経済2025年|最新経済市場動向を読み解く
AI(人工知能)は、世界各国の経済成長を支える基盤技術として注目されています。 とりわけベトナムでは、政府が国家戦略としてAIの導入を明確に位置づけ、経済、教育、公共行政、スタートアップ育成まで多岐にわたる分野で取り組みを強化しています。 この記事では、「ベトナムAI経済2025年」レポートをもとに、マクロ経済との接続性、国家戦略、セクター別の導入状況、スタートアップ・投資動向、そして将来の展望について解説します。 これらに当てはまる方におすすめの記事となっています。これを読めばAIがもたらすベトナム経済の進化と、その背景にある政策と市場構造を総合的に理解することができます。